皆様、おはようございます。
星見です。
自由が良いです。真に自由が良いです。
真に自由とは何か。
自(みずからに)由(よる)
自由による見解を色々調べてみました。
自由とは、したいことができることである。ただし、人に害を加えない範囲で。自由には、気持ちよさや楽しさ、解放感が伴う。その解放感には、幅がある。そして、日常にない感じが、必ずある。

これ、もはや言ってる意味が分かりません。人に危害を加えない範囲で自由というのは、真に自由ではないでしょう。
じゃあ何か?人殺しをしてもいいのか!なんて思ってしまいそうですが、その人自体が、何かに囚われて人殺しをしている時点で、その人は自由ではありません。今回は真に自由で、社会的自由ではありません。
そもそも、自由というのを、他の人と話をして決めること自体が自由ではないし、もうめちゃくちゃです。
仏教的な自由はコチラに書いてあります
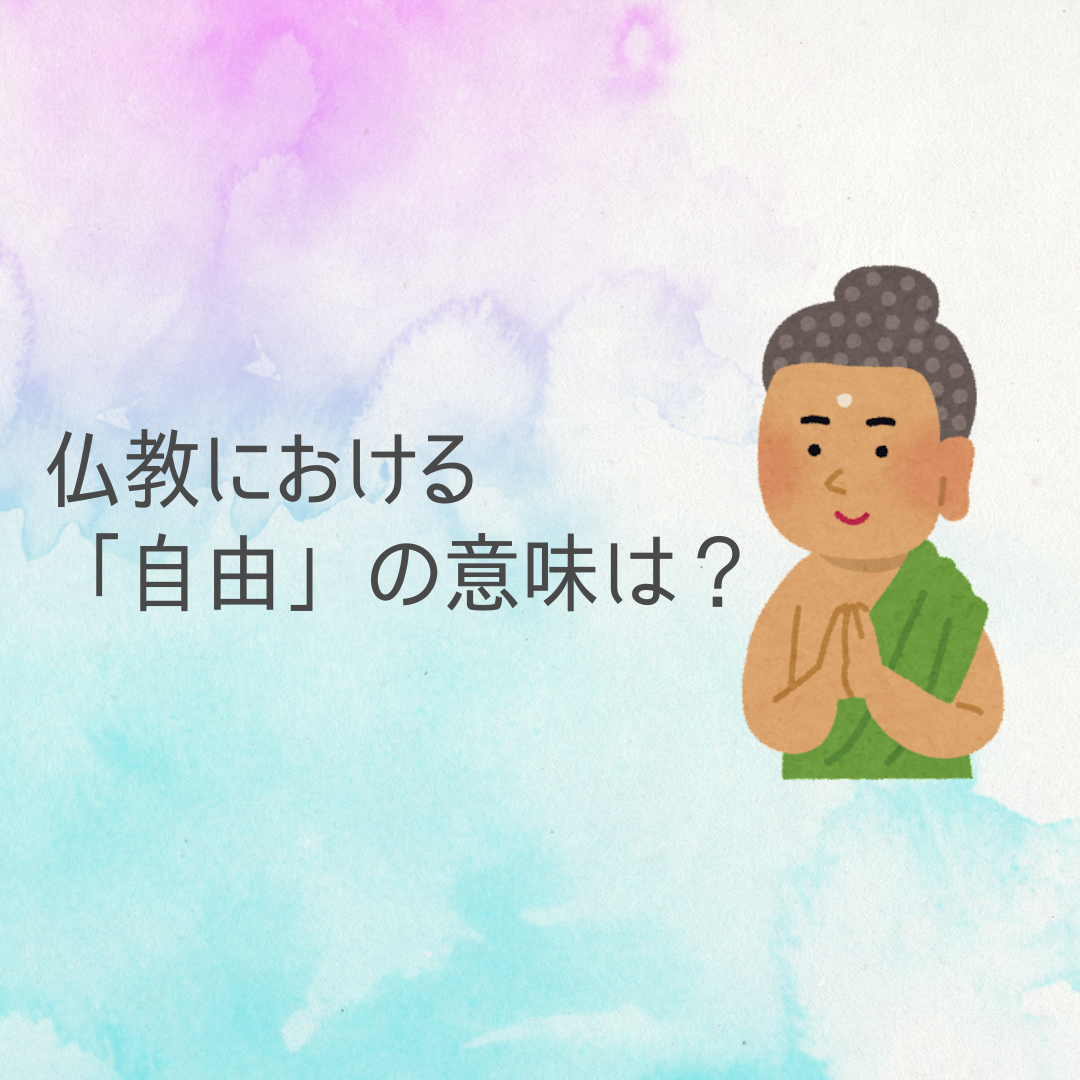
A.お釈迦さまの教えでは自由とは「自らに由る」もの。
B.つまり、自由は内側から湧き上がるものです。
C.この観点からすると、「自由」は外部の世界が私たちに与える何かではなく、自分自身の内側から生まれ出る真実の理解と、それによって得られる深い平和を表しています。
D.自己中心的な欲やわがままから解放された自由な状態、無我の状態に達することで、全ての存在を平等に見ることができるようになるでしょう。
と書いてあります。分かりやすい様にA~Dに書きました。
「真実の理解」なるものと「深い平和」が自由なのかはひとまず置いておいて、「全ての存在を平等に見る事ができる」は私という主体からは解放されていないので、自由な感じは無いです。
他にも
「自灯明・法灯明」とは
「さとりを求めるには人任せではなく、自ら(自灯明)と仏の教え(法灯明)をよりどころにしなさい」と弟子たちに伝えた教えです。
「仏の教えをよりどころにしなさい」の部分ですが、これは支配的なので、真に自由な感じはしないですね。自由について埒があかないので、今回はgrokさんに聞いてみます。まずは西洋哲学から。
- ジョン・ロック(John Locke)
-
自由は「自然権」の一つであり、個人が自己の生命、自由、財産を保持する権利を持つと主張。
社会契約論の枠組みで、自由は法の下で他者を害さない範囲で保障されるものと考えた。
「自由とは、人が自分の行動を自分で決定し、自分の意志に従って行動できる状態である。 - ジャン=ジャック・ルソー(Jean-Jacques Rousseau)
-
ルソーは「自然の自由」と「市民的自由」を区別。自然状態では無制約な自由があったが、社会契約により市民的自由が生まれる。
真の自由は「一般意志」に従うことで実現されるとし、個人の欲望を超えた共同体の意志が自由の基盤となる。
「人間は自由に生まれ、しかし至るところで鎖につながれている。」イマヌエル・カント(Immanuel Kant)
-
自由は道徳的行為の前提であり、人間が理性に基づいて自律的に行動する能力を指す。
自由は外的な制約からの解放だけでなく、自己の欲望や衝動からの内面的な自律を含む。
「自由とは、理性によって自己の法則を定め、それに従うことである。」
ジョン・スチュアート・ミル(John Stuart Mill)功利主義の立場から、個人の自由を最大限に尊重すべきと主張。特に「危害原則」を提唱し、他者に害を与えない限り自由が保障されるべきとした。
言論や思想の自由を重視し、個人の自己実現と社会の進歩に不可欠と考えた。
「自由とは、個人が他者を害さない限り、自分の幸福を追求する権利である。」フリードリヒ・ニーチェ(Friedrich Nietzsche)
自由は「自己超克」や「力への意志」の表現として捉えられ、伝統や道徳の枠組みを超えて自己を創造する行為に結びつく。
真の自由は、強い個人が自らの価値を自分で定め、運命を愛する(アモール・ファティ)姿勢から生まれる。
「自由とは、自分自身になるための戦いである。」
ジャン=ポール・サルトル(Jean-Paul Sartre)実存主義の立場から、人間は「自由に運命づけられている」と主張。人間には本質がなく、自由な選択を通じて自己を定義する。
自由は同時に責任を伴い、選択の重さを引き受けることが人間の条件。
「人間は自由である。逃げ道はない。」
アイザイア・バーリン(Isaiah Berlin)「消極的自由」と「積極的自由」を区別。消極的自由は外部からの干渉がない状態、積極的自由は自己実現や自治の能力を指す。
両者のバランスが重要だが、積極的自由の名の下に強制が生じる危険性を警告。
「自由とは、干渉されずに選択できること、そして自己の目的を追求できることである。」
まとめ
西洋哲学に自由を求めると、時代背景や、特色がでています。この文ではまだ真に自由にたどり着いてなさそうですね。思考からの自由は中々抜け出せなさそうですね。
続いてGrokに東洋哲学の中での自由について聞いてみます。
老子(道家)
老子は『道徳経』で「無為自然」を説き、人間が自然の流れ(道)に従い、強制や作為を離れることで真の自由を得られると考えました。自由とは、社会的規範や欲望による束縛から解放され、道と調和したシンプルな生き方にある。
自由の視点: 自由は「無為」によって達成される。権力や名誉、物質的欲望から離れ、自然体で生きることが究極の自由。
例: 「知足者富」(足るを知る者は富む)―欲望を抑え、ありのままを受け入れることが自由への道。
荘子(道家)
荘子は相対主義と絶対的自由を強調し、世俗の価値観や二元的な判断(善悪、貴賤など)を超えた「逍遥遊」(自由な精神の遊泳)を理想としました。万物と一体となり、自我を超越することで心の自由を得る。
自由の視点: 自由とは、心が一切の束縛から解放され、宇宙と調和すること。「胡蝶の夢」のように、固定された「私」を超えた境地が自由。
例: 「至人無己」(至人は自己がない)―自我を捨て去ることで完全な自由が実現する。
孔子(儒家)
儒家では自由は「仁」や「礼」の実践を通じて得られるものとされます。孔子は『論語』で「七十而従心所欲、不踰矩」(70歳にして心の欲するところに従っても、規範を越えない)と述べ、道徳的修養を通じて内面的な自由を獲得する道を示した。
自由の視点: 自由は単なる放縦ではなく、自己を律し、倫理的秩序の中で調和を保つこと。修養を積んだ結果、心が自然に正しい道に従う状態が自由。
例: 個人の欲望を抑え、礼に従うことで社会と調和し、内面の平安(自由)を得る。
孟子(儒家)
孟子は人間の「性善説」を基に、人が生まれながらに持つ善の心(仁義礼智)を発揮することで自由な精神を育めると説いた。外的な強制や利害に左右されない「浩然之気」(大いなる気)を養うことが自由への道。
自由の視点: 自由とは、外部の圧力や誘惑に動じず、内なる善に基づいて行動すること。
例: 「富貴不能淫、貧賤不能移、威武不能屈」(富貴に惑わされず、貧賤に心を移さず、権力に屈しない)―これが自由な「大丈夫」の姿。
釈迦(仏教)
仏教では、自由は「解脱」や「涅槃」の境地として理解されます。釈迦は、執着(貪・瞋・痴)からの解放が真の自由であり、悟りを通じて苦しみの輪(輪廻)から脱却すると説いた。
自由の視点: 自由とは、欲望や自我の幻想から解放され、無我の境地に至ること。心の平静(寂静)が究極の自由。
例: 四聖諦や八正道を通じて、苦の原因を断ち、解脱に至るのが自由への道。
龍樹(ナーガールジュナ、仏教)
中観派の祖である龍樹は「空」の思想を展開し、すべての現象は固定的な実体を持たないと説いた。自由とは、固定観念や二元対立を超え、「空」の智慧によって心を解放すること。
自由の視点: 自由は、執着や偏見から離れ、事物の本質(空)を見極めることで得られる。
例: 『中論』で「縁起」と「空」を通じ、絶対的な自由を悟る。
西洋哲学的には、外的影響からの自由が主観に置かれている感じがありますが、東洋哲学は内面的な解放を目指している様に感じますね。
我々西洋化された東洋人としては、両方の気持ちがわかると言ったところでしょうか。私はアホなので、結局同じ事いってね?と思ってしまうのですが、皆様いかがでしょうか。
また、真に自由を得た人が言った言葉なのか、その途中の人が言った言葉なのか、それを言葉で言い表わしたらそう言うしか方法がないのか、私みたいなアホが拡大解釈して後世に伝わってしまっているのか、全くわかりません。
ただ、これが正しいのだと決めた瞬間に、自分の自由が定義され、真に自由にはなれない気もします。
よって真に自由であるということは、言葉で定義してはいけない。自分で道なき道を進んでいくしかありません。
これで終わりにしようと思っているのですが、既に続編を書いてしまっているので、次回は真に自由になろうぜ②でお会いしましょう。
